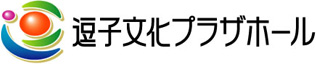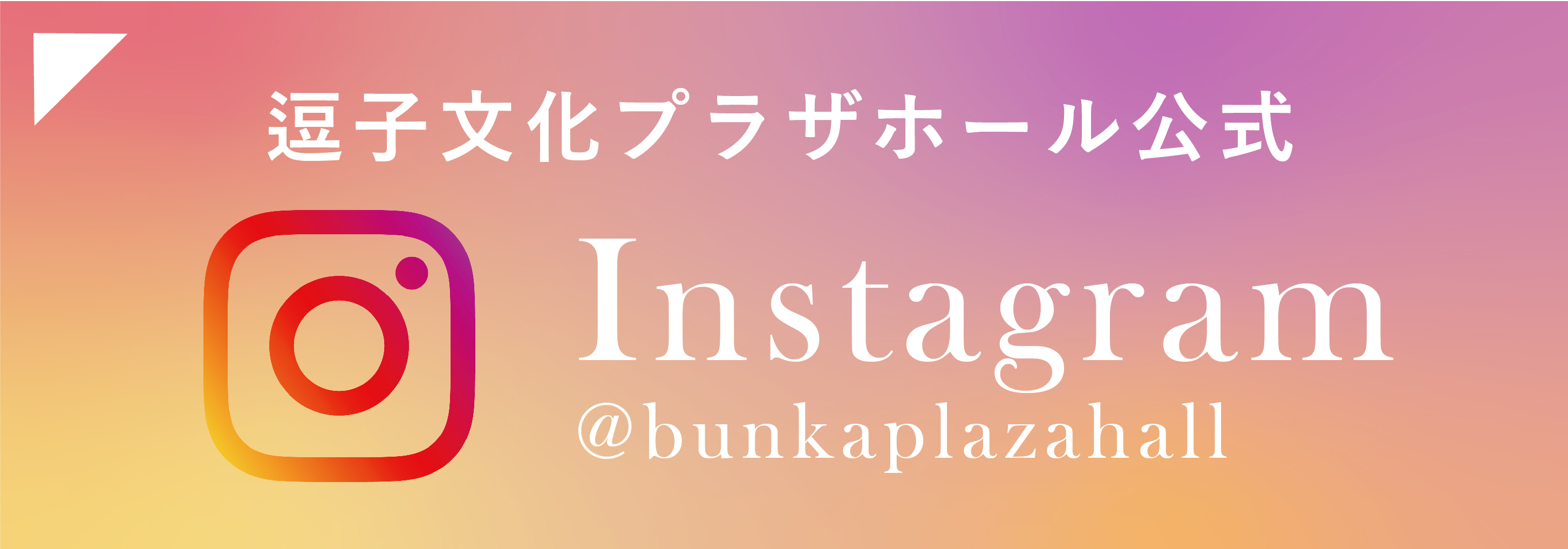当ホールの情報発信ボランティアによるレポートです。イベントの雰囲気や感想を発信する活動をしています。
この日の会場はどちらかというと年配の方でいっぱいだったが、中には小学生らしいお子さんたちの姿もあった。
老若男女を問わず、その場に集まった人たち全員の気持ちの共通項。それは、能狂言という我々日本人の間に長きに渡って伝わる『伝統芸能』を楽しみたい。そして我々の祖先たちが残してきてくれた『文化』に触れたい。そういうものなのではないかと思う。
この文章をここまで読みながら「能ってどんな舞台なの?」、「狂言って字だけ見るとちょっと・・・」という方もいらっしゃるのではないかと思う。
私も皆さん同様、それほど詳しいわけではなかったので、会場に向かう前に予習した内容を、かいつまんでお伝えすると・・・。能は約600年の歴史を持つ、舞踏・劇・音楽・詩などの要素が交じりあった舞台芸術。狂言は能とほぼ同じ頃に発生した、能とセットで演じられることの多い演劇。見るものを幻想的な世界に引き込む能に対して、狂言は笑いで観客をリラックスさせる。おおざっぱにいうとそんなところである。
さて、会場はいよいよ開演である。仕舞(面・装束をつけず、紋服・袴のまま能の一部を舞う略式上演)「野宮」に凝縮された源氏物語の世界を感じ、藪医者と地面に落下してきた雷様とのやりとりを滑稽に描いた狂言「雷」に笑った後、いよいよメイン演目の能「雷電」である。
雷神と化した菅原道真の荒れ狂う姿が迫力たっぷりに表現され、私を含めた観客は皆、圧倒された。特に舞台終盤で描かれた雷神・道真と、彼の恩師天台座主法性坊の法力による死闘。そこには、今はやりのレーザービームなどによる視覚効果も、大音響による効果音もなかった。そこにあったもの。それは不気味な能面と、華麗な衣装。場面を盛り上げる囃子、そして舞台せましと繰り広げられる舞、で表現された日本の伝統芸能ならではの美しさと気迫であった。
この舞台で演じられたものの本質を皆さんに伝えきることは、ここで与えられた文字数では到底不可能である。だから私が最後に申しあげたいこと。それは「是非、次回は(も)会場に足を運んで、この能と狂言の世界に触れて欲しい。皆さん自身の目で、耳で、そして体全体でこの世界を体験して欲しい」ということである。
日本人として誇りに思える世界。それがここにはあるということをお伝えして、私のレポートを終わりたい。
ボランティアライター 浅野修弘
***************************************************
敷居の高さに懸念しつつも、いつかは鑑賞してみたいと思っていた能狂言。少しばかりの知識を仕入れて緊張しつつ会場に向かいました。女性ばかりの会場を想像しましたが、男女数同じぐらいの観客の方々が始まりを待ち遠しくされています。
舞台には能舞台が組まれていました。演劇やミュージカルに比べてとても簡素ですが、檜で作られた舞台は、品格があり奥ゆかしい風合いで、長い年月の間、丁寧に手入れをされてきた事が伺えます。背景に描かれた、にぶい光があたる松の絵をみていると背筋が伸びるような気持になります。
能の普及活動に尽力されている柴田稔さんが本日の公演は仕舞・狂言・能である事と、それぞれのストーリーと見所をわかりやすく説明してくれました。
いよいよ仕舞『野宮』が始まります。『野宮』は源氏物語の六条御息所のせつない恋心を描いた名曲です。仕舞には、セリフはなく、面や装束をつけずに紋服袴で山場の部分だけを舞と地謡で演じます。視覚的な華やかさが抑えられた分、地謡の響きや舞の所作の美しさに日本芸能文化の本質が浮かび上がるかのようでした。さらに狂言、能へと続きますが、この二つはとても対照的で、狂言はセリフを中心に物語が進み、オチもあり愉快で賑やかな舞台です。笑いの芸術とも言われます。一方で、能は亡霊や幽霊が出てくる話が多いと言われます。両者共通するキーワードは雷。昔人々は、雷は神様からの強いエネルギーとして怖れ、あがめてきました。それぞれの物語の中で雷がどのように表現されるのかが見所です。
狂言の『雷』ではまぬけな雷と藪医者のパロディが繰り広げられます。語りも動きもコミカルで、自分をあえて藪医者と名乗る絶妙な間合いは、今日のお笑いの原点かもしれません。いつの時代も笑いは場を明るくしてくれます。
能『雷電』は無念で死んだ菅原道真の復習の手段として雷が出てきます。面で表情こそ見えないものの、恨み、つらみのおどろおどろしさがダイナミックな所作によって表現されます。不気味ですが、怨念にまみれて舞う姿を美しいとさえ感じてしまいます。道真の激しい恨みで立ち込められた空気がふと悲しみにそして穏やかに変わる瞬間がありました。ああ、道真はやっと浮かばれたと安堵したシーンでした。喜怒哀楽を上品に凛々しく表現する能狂言の世界に、尊く誇り高さを感じた貴重な時間でした。
ボランティアライター 山上真琴