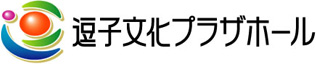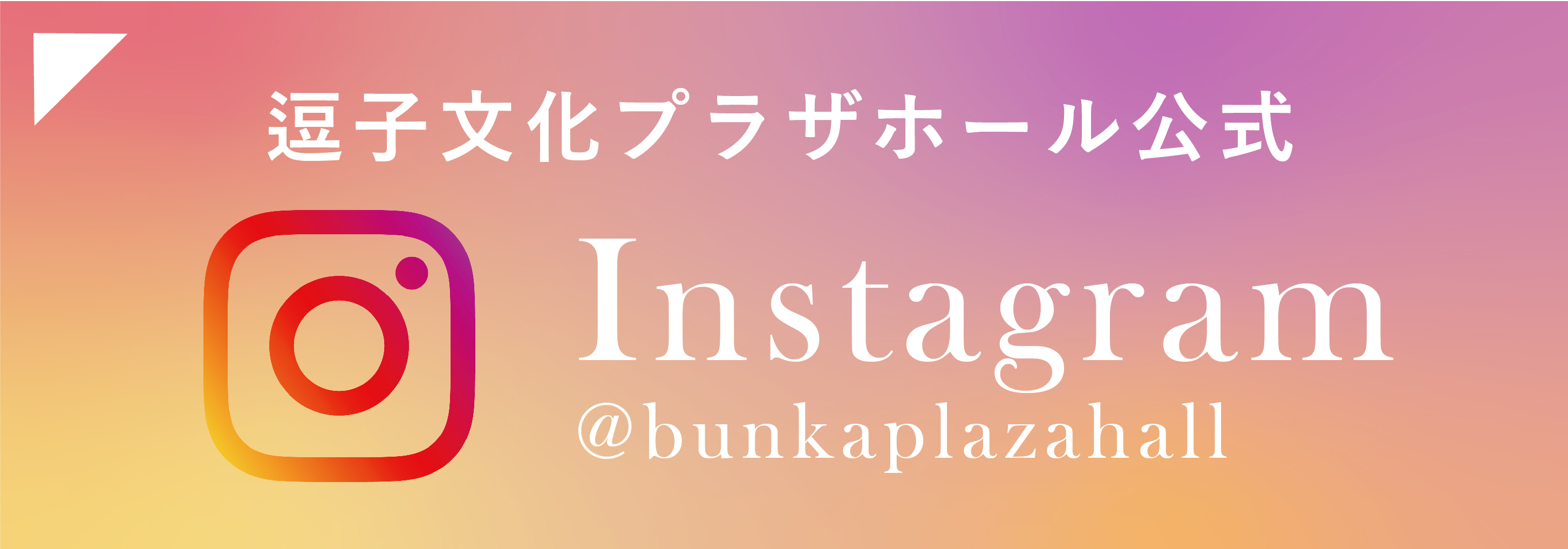当ホールの情報発信ボランティアによるレポートです。イベントの雰囲気や感想を発信する活動をしています。
***************************************************
団名「ウェールズ」ときいて英国に何かの縁があるのかと思っていた。本当は、ラテン語で「誠実」「真実」という意味があり、作曲家や自分たちの音楽に誠実であり続けたいという気持ちでウェールズと名付けたそうだ。(ZUSHIBunkaPlazaHall ホール&ギャラリーニュースのインタビューより)
爽やかな風が吹くように4人の男性が舞台を歩いてくる。最初の曲は、客席全員が好きだと思われるモーツァルトの《セレナード第13番 ト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K.525》より第1楽章で始まり、会場は高貴な香りが流れた。
ヴァイオリン担当の﨑谷さんがマイクを握り、ややシャイな感じで今回演奏する室内楽の魅力などを語りコンサートをつむいでいき、モーツァルト《弦楽四重奏曲第15番 ニ短調「ハイドン四重奏曲第2番」K.421》の演奏。小さな音域も、エントロピー(物質的な熱力学的な状態を示す物理量のひとつ:百科辞典マイペディアより)が増大するように彼らの秘めたる情熱をひらめかせて、綺麗な曲を醸し出している。
休憩時に、ホワイエに出ると、コーヒーなどを飲む人たちのうっとりしたような笑顔が一杯。後半、ベートーヴェンの《弦楽四重奏曲第9番 ハ長調「ラズモフスキー第3番」op.59,No.3》。の演奏は、JAZZで身体がスイングするのと同じような感覚を覚えた。私にとってベートーヴェンの新たな魅力を感じさせてくれる演奏、音楽だ。
アンコール曲、モーツァルトの《ディヴェルティメントK.138》より第2楽章で、彼らは風のように姿を消す。自宅への帰り道。体が軽やかに感じた。
友人たちの間で「528ヘルツ」が流行っている。モーツァルトなどの曲に多く使われている音の高さだそうだ。ストレスが目いっぱいの日々「528ヘルツ」の音を聞くと、癒されるとのこと。医学的なことはよくわからないが、副交感神経を刺激して、ストレスで高まった交感神経とのバランスをとることによりリラックスするそうだ。
リゾートタウン逗子。素敵な海や山とともに室内楽を楽しみながら明日への活力をもらえた。
情報発信ボランティアライター 海原弘之
***************************************************
黒い詰襟。シックな装い。まるでマジシャンのよう。若きスタイリッシュな男性4人が、静かに、颯爽と登場する。いきなり始まるインパクトのある出だし。モーツァルトの名曲《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》。ヴァイオリン2人とヴィオラとチェロ。皆、抑え気味のアクションだが、乱れなく4つの音がシンクロする。モーツァルトらしい明るく奔放で流麗な曲。7分間の短い演奏。貴族の社交場の喧騒が頭に浮かんだ。2曲目。同じくモーツァルトの《弦楽四重奏曲第15番》。いわゆるハイドンセットといわれる、6曲の弦楽四重奏曲の第2番。全4楽章。唯一の短調作品。だから彼らの演奏も、哀愁が漂う。特にヴァイオリンの響きが切ない。モーツァルトらしからぬ悲しい曲。息子を亡くしたときに作った曲らしい。静かに聴き入ってしまった。
休憩の前に、後半の曲の説明。今度はベートーヴェンの弦楽四重奏曲。どんなストイックな演奏になるのだろう。期待を胸に残して休憩に入る。
後半。ベートーヴェンの中期の傑作《ラズモフスキー第3番》。全4楽章。ベートーヴェンの印象は、スクエアで男性的かつ華麗。モーツァルトとは好対照。第1楽章は静かな導入から、ヴァイオリンの軽やかなソロが次第に早く、大きく、スリリングな展開。第2楽章は一転して重苦しい調べに。チェロの弦をつまびく音が憂鬱に響く。第3楽章はのどかに美しいアンサンブルでフィナーレにつなぐ。第4楽章はベートーヴェンの真骨頂。ソナタ形式でドラマチックな展開に。ヴァイオリンとチェロの高・低音が、極端な強弱をつけて徐々に激しさを増して掛け合う。テンポを速めた4つの弦楽器が、歓喜のクライマックスに向けて圧倒的な迫力で共鳴する。室内楽が、まるで交響曲のように壮大に聴こえる。そして大団円(フィナーレ)。でも4人は表情も変えず淡々と頭を下げ、スマートに退場する。
興奮冷めやらぬまま、アンコールに応える。再びモーツァルト。《ディヴェルティメントK.138》より第2楽章。女性的で繊細なやさしいハーモニーに、先程までの興奮が一気に静まり、ホッと力が抜ける。絶妙な構成だ。しかし、ウェールズの4人は、1人を除き一切口を開かず、徹頭徹尾、クールである。そして、変わらぬスタイルで、見事に繊細と荘厳、軽妙と重厚を奏で分ける。やはり4人はマジシャンだった。
情報発信ボランティアライター 三浦俊哉
***************************************************
初冬とはいえ穏やかな好天に恵まれた三連休の最終日、なぎさホールに出かけた。
弦楽四重奏の演奏会は久しぶりだ。連休で遠出した人が多かったのだろう。お客の入りはイマイチ。でもそれだけに、来ている人たちは年齢を問わず熱心なクラシックファンが多い。
曲目は、モーツァルト2曲とベートーヴェン1曲で、古典派の巨匠であり対照的な2人の組み合わせ。
最初の曲はあまりに有名な《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》。耳馴染みの曲からのスタートで聴く方も肩に力が入らなくてすむ。コンサートに馴染むのにベストの選曲だ。
2曲目は同じモーツァルトでも対照的な曲想で、いかにも二短調の暗い感じ。作曲されたのはモーツァルト自身が息子を病で亡くした直後だったらしいので、この曲想は頷ける気がする。この曲で一番痺れたのは、ヴァイオリンとチェロのピッツィカートが掛け合うところ。心の揺らぎをよく表現している。
この楽団のメンバーは桐朋学園出身の仲間たちで10年以上活動を共にしているだけに息もぴったりあっている。曲想の違う曲をどれも作曲家が意図したとおりに再現してみせるところに演奏力の高さを感じる。
休憩後は、お待ちかねベートーヴェンの《ラズモフスキー第3番》。40年くらい前には、FMなどでよく聴いた覚えがあり懐かしい。ベートーヴェンらしく、曲は起承転結が明確でメリハリが効いている。聴き終わったときにはベートーヴェンは言いたいことを言い尽くし、聴く方も聴くべきものを聴き尽くした感が強く残る。すべて出し尽くした完結性がある。観客席は満足感が漂い満場の拍手!
アンコールはまたモーツァルトに戻って、《ディヴェルティメントK.138》より第2楽章。ラズモフスキーで高まった心の緊張感をほぐされた。まさに、食後のデザートが出てきたようだ。選曲の良さと演奏力の高さで、心の掃除と右脳の刺激ができた素敵なコンサートになった。
情報発信ボランティアライター 福岡伸行
***************************************************
ウェールズ弦楽四重奏団・・・英国人?と思いきや、チラシに出ているのはどこから見ても東洋人の四人組。実は2006年に桐朋学園の学生四人で結成されたクァルテット、すでに各種の賞を受賞し華々しく活躍しているという。思えば私は弦楽四重奏団のコンサートというのは生まれて初めてだ。何となく豪華客船の高級レストランで流れる音楽、というイメージだが、さてどんなものだろう?
コンサートといえば、大抵女性客の方が多いように感じるが、本日の会場はお洒落な年配の男性が多い感じ。四重奏が好きで来た、という人たちに違いない。開幕のベルが鳴り、一曲目は《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》。小さな夜の音楽、という意味のこの曲は、明るく軽快なオーケストラで聞きなれた曲だったが、四重奏団が奏でると、ぴたりと息が合いながら、それぞれの楽器の音が一つ一つ際立って聞こえる。一糸乱れぬ調和と共に、その構成者各人が個性と技を存分に際立たせて演奏している。そしてその透き通ったピアニシモの柔らかく美しいこと。まるで四つの楽器で一つの精緻で繊細なレース編みを編み出しているような音色だ。フォルテも温かみと節度ある音が一つになって、力強くもまろやかで、最近聞いた19世紀のピアノを使ったコンサートの音を思い出した。ここで音楽家が挨拶に立ち、「次は弦楽四重奏曲第15番ニ短調で、これが同じモーツァルト?と思うような曲、どうやら彼の息子が亡くなった頃に書かれたもので、作曲家の内面がより深く出ている」、という。
一曲目は軽やかに気持ちよくこのまま眠ってしまいたい感じがしたが、この二曲目は打って変わって短調の曲、ここでは力強いが自制のある音と弱音の入れ替わりがより際立って聞こえるように感じた。演者が、「次の曲はベートーヴェンの《ラズモフスキー第3番》、いろいろな曲の中で、作曲家が最も表現したいことが出ているのが弦楽四重奏だと思う、演奏に集中したいので今お話ししておきます」、と言って休憩に入った。
20分後に演奏が始まると、今度は一音目から、おっ、という感じ。四重奏の醍醐味は、やはりベートーヴェンなのだろうか?チェロのピチカートが入る斬新さ、そして第四楽章でヴィオラとヴァイオリンが掛け合いをするような緊張に満ちたアップテンポの演奏に思わず息を飲んだ。ヴィオラってすごいんだ!そしてこのそれぞれの楽器の激しさが、高度の集中力によってなぜか一つの大きな音の中にぴたりとシンクロナイズする様子は、これは高等数学の公式の持つ完璧な美しさ、というものに近いのではないか?と感じた。うーん、さすがお見事!弦楽四重奏という新たな世界を、発見させてもらったひと時だった。
情報発信ボランティアライター 不破理江
***************************************************